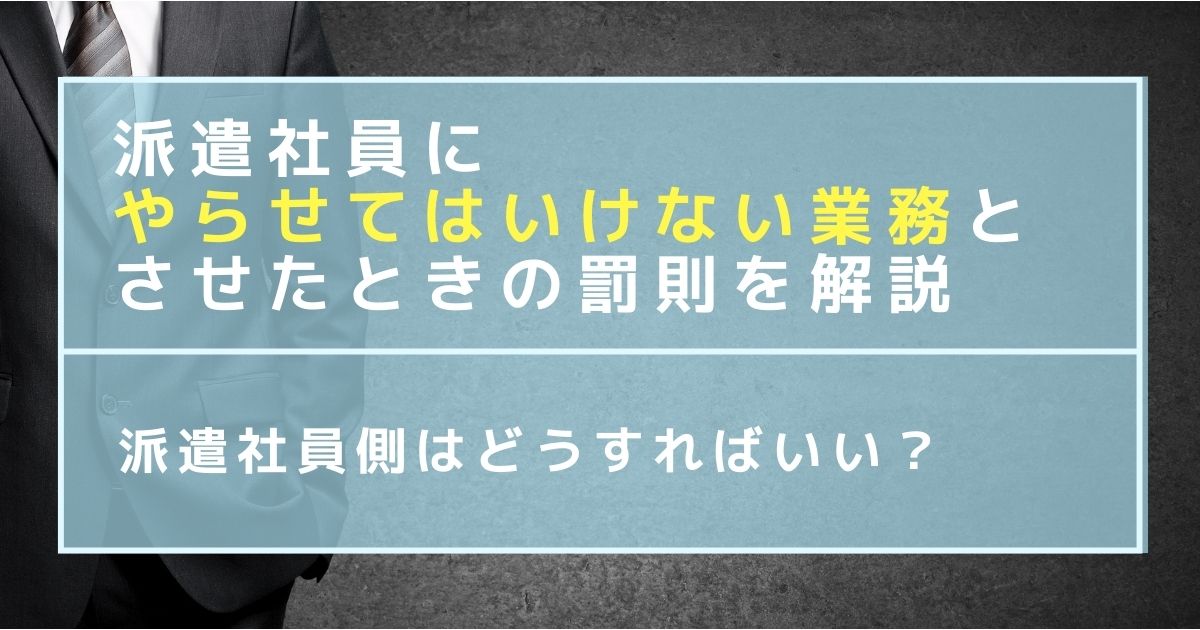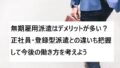派遣社員には、やらせてはいけない業務があるのをご存知でしょうか?
派遣社員の業務は契約書に定められているものに限定され、労働者派遣法で禁止されている仕事や専門性の高い仕事、労働者の安全確保が難しい業務なども与えてはいけません。
もし派遣社員にやらせてはいけない業務を与えれば違法となり、会社側へ大きな罰則が科せられる可能性があります。
このコラムでは派遣社員にやらせてはいけない業務の詳細と、派遣社員がやってはいけない業務を派遣先企業に指示された場合の対処法を紹介しますので、正しい知識を身に着けましょう。
派遣社員から正社員を目指すなら通常の転職サイトよりもサポートが充実した転職エージェントを使うのがおすすめです。
未経験職種・業界への転職や正社員になるのが初めての方は提出書類の作成や面接テクニックをエージェントの人からサポートしてもらいましょう。
| おすすめの3サービス | 公式 |
|---|---|
|
リクルートエージェント |
公式 |
|
JAIC |
|
|
・5分の質問で自分の市場価値がわかる |
公式 |
派遣社員にやらせてはいけない業務がある!契約外業務との違いとは
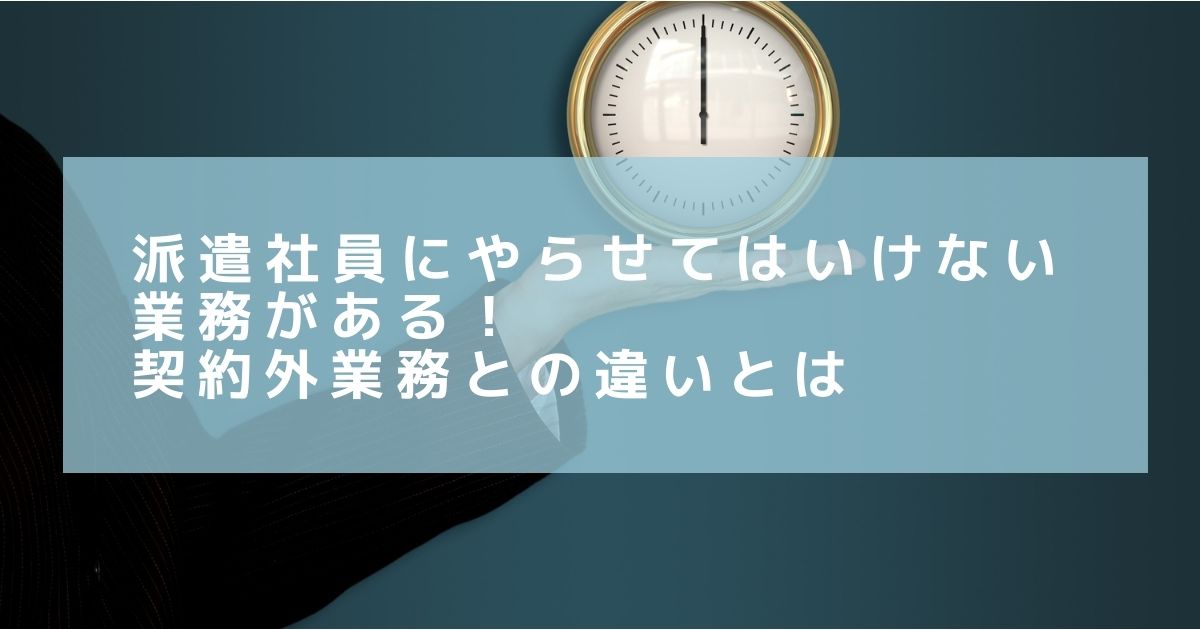
派遣社員の仕事は派遣契約で定められた範囲内の業務に限るので、派遣先が勝手に判断して契約にない仕事をさせてはいけません。
また、通称「労働者派遣法」と言われる「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」及びその施行令等で指定されている業務も禁止です。
労働者派遣法で派遣が禁止されている業務について
派遣法では業務の専門性の高さや労働者の安全確保の面から派遣が禁止されている業務があります。
- 港湾運送業務
港湾における、船内荷役・はしけ運送・沿岸荷役やいかだ運送、船積貨物の鑑定・検量等の業務 - 建設業務
土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの準備の作業に係る業務 - 警備業務
事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地における、または運搬中の現金等に係る盗難係や、雑踏での負傷等の事故は発生を警戒し、防止する業務 - 病院・診療所等における医療関連業務
医師、歯科医師、薬剤師の調剤、保健婦、助産婦、看護師・准看護師、栄養士の業務(可能の場合もある) - 弁護士、外国保険労務士等のいわゆる「士」業務
弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務や、建築士事務所の業務等
(公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士等の業務では一部で労働者派遣は可能)
弁護士や社会保険労務士などのいわゆる「士業」は派遣法の適用除外業務ではありませんが、当該業務の定める各法令の趣旨から 派遣が禁止されています。
派遣が禁止されている業務の中でも一部派遣が可能な業務があること、業務を行う場所や頻度、適用除外業務との類似性が高い場合には派遣禁止業務と見なされる場合があることなど、派遣可能か否かを明確に分けることは難しく、派遣会社でも判断に迷うケースは多いです。
二重派遣をさせてはいけない
二重派遣とは、派遣社員を受け入れた派遣先が別の企業に労働者を派遣することです。
雇用責任の所在が不明瞭になるリスクや給与が不当に低くなるリスクから労働者を守るため、職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)と労働基準法第6条(中間搾取の排除)から違法行為として定められています。
(参照:e-GOV法令検索『職業安定法』、e-GOV法令検索『労働基準法』)
契約外業務をさせてはいけない
派遣会社と派遣先企業が詳細に決めた派遣契約に基づく仕事が派遣なので、契約で定められていない業務をする、契約書とは異なる時間や場所で働かせる行為は契約違反となります。
契約外業務とならないためにも、派遣会社と派遣先企業の契約では派遣労働者が従事する業務内容を具体的に記載し、複数の業務に従事する場合は全ての業務内容について記載しなくてはなりません。
派遣社員は業務内容に記された業務が仕事になるので、派遣社員の同意があっても契約違反となります。
契約とは明らかに異なる業務をやらされるのは契約違反と分かりやすいですが、コピーをとるなどの付随業務や雑用までは記載されないことも多い状況があります。
トラブル防止や派遣社員に不信感を抱かせないために、派遣会社は以下のような行動を取って、契約で前提となっている業務の範囲を事前に把握しておくことが大切です。
- 業務内容に付随する業務の発生有無を説明する。
- 労働者は業務内容に記載された仕事の範囲はどこまでなのか確認する。
契約なしの出張
派遣の仕事はオフィスワークが多いですが、職種によってはお客様の所へ出張に行く必要が生じる仕事もあります。
業務上突然発生し得る出張であっても、派遣会社と派遣先企業の間で出張費用、期間、手当などの細かな取り決めがされなくてはなりません。
派遣契約で明記していない出張をさせられないのはもちろん、出張をさせてもいいことになっていても出張費や手当などの負担でトラブルにならないよう確認が必要です。
違う部署での仕事
派遣契約では業務内容や就業時間、残業有無などと併せて就業場所や所属部署も明記しなくてはならないので、契約で定められた場所や部署以外での業務は契約違反となります。
以下は契約違反の一例です。
いずれも契約にない仕事ですので、契約違反として扱われてしまいます。
就業時間後の飲み会や接待
就業時間後の飲み会は業務内容に含まれないので、歓送迎会を目的とした飲み会であっても、派遣社員の参加は必須ではありません。
客先での接待は仕事の一環ではありますが、派遣社員は残業無しで契約していることが多いので、派遣先が派遣社員へ参加を強制することは禁止です。
サービス残業や掃除は契約に書かれて入ればOK
以下の条件全てを満たしている場合、派遣先企業は労働者を残業させることが可能です。
- 契約で残業が発生する場合があることを明記している。
- 1日8時間、週40時間以内に収まる残業である。
- 残業時間に応じて残業代を支払う。
もし1日8時間、週40時間を超えて労働させるには36協定の締結が必要で、派遣会社が36協定の締結・届出をしている場合に限り派遣労働者に36協定が適用されるので、派遣会社が締結していなければ、派遣社員は法定労働時間を超える労働はできません。
掃除や電話対応といった雑用に当たる業務も契約書に明記されていたり、契約時に同意が得られている場合のみ派遣社員に業務として与えられます。
「ちょっとの残業」や「掃除くらいやってくれてもいいのに」という派遣先都合の考えがあっても、契約外業務は通りませんので注意しましょう。
派遣社員の判断業務は法律上問題なし
派遣社員の判断業務に関しては、特に法律上で定められていませんので、派遣先の社員が常勤していなくても問題はないです。
ただ、いざという時に派遣社員に責任は負わせることは難しいですし、社員が不在の間に起こった労災事故や安全衛生管理など、労務管理上のリスクを回避するためにも派遣先の社員は常勤するようにしてください。
派遣にやらせてはいけない業務をさせた派遣先の罰則とは?
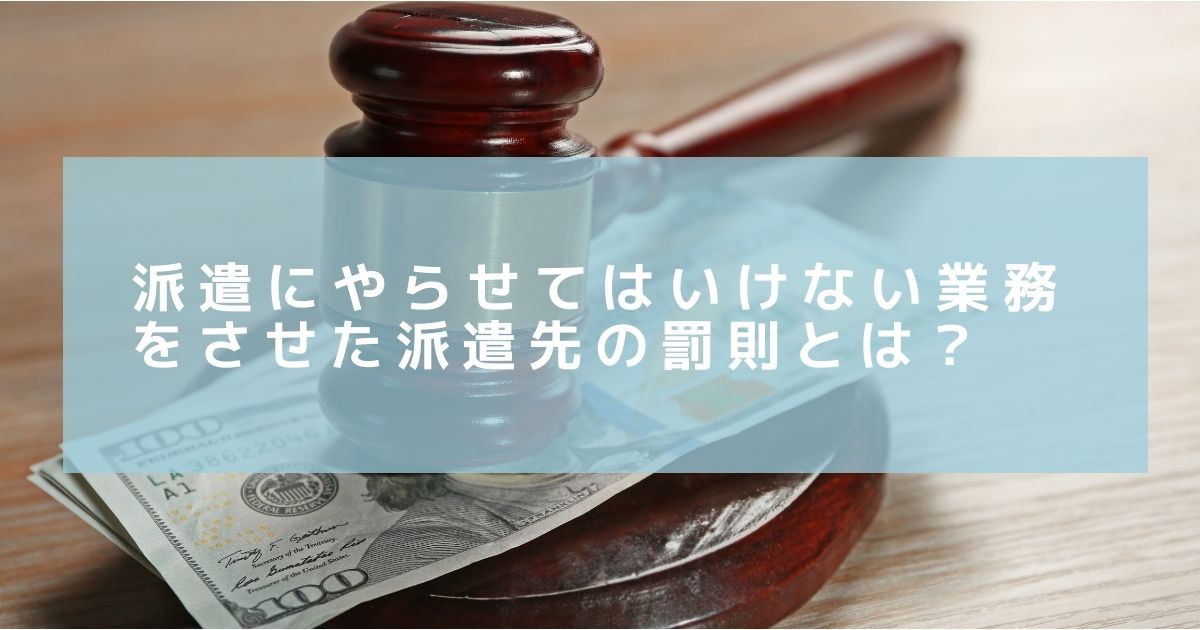
契約外の業務をさせたり、派遣労働者は労働者派遣法で禁止されている業務に就かせられなかったりすることをご紹介してきましたが、もしこれに違反した場合の罰則はどうなるのでしょうか?
違反した場合、派遣会社や派遣先企業は行政処分という社会的信用悪化だけでなく、罰則が下されるので、具体的な内容を確認してみましょう。
労働者派遣法で派遣が禁止されている業務を行わせた場合の罰則
労働者派遣法で派遣が禁止されている業務を行わせた場合、業務を行わせた側は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を支払わなければなりません。
二重派遣を行った時の罰則
二重派遣は、職業安定法の第44条に抵触する行為ですので、厚生労働大臣の許認可なく労働者供給行為を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
さらに、派遣先が他の企業に派遣社員を派遣し、手数料を得た場合には、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。
契約外業務を行わせる罰則と派遣会社から指摘を受けるリスク
派遣先が派遣社員に契約外業務を行わせた場合、まずは派遣会社の担当者から契約内容の再確認と業務改善について打診があります。
業務内容を改善させない場合には、派遣会社から派遣社員を斡旋してもらえなくなるだけでなく、訴えられた場合に30万円以下の罰金を科される危険性があります。
(参照:厚生労働省『第13 違法行為による罰則、行政処分及び勧告・公表』)
派遣社員は契約外の仕事をどの程度許容するもの?
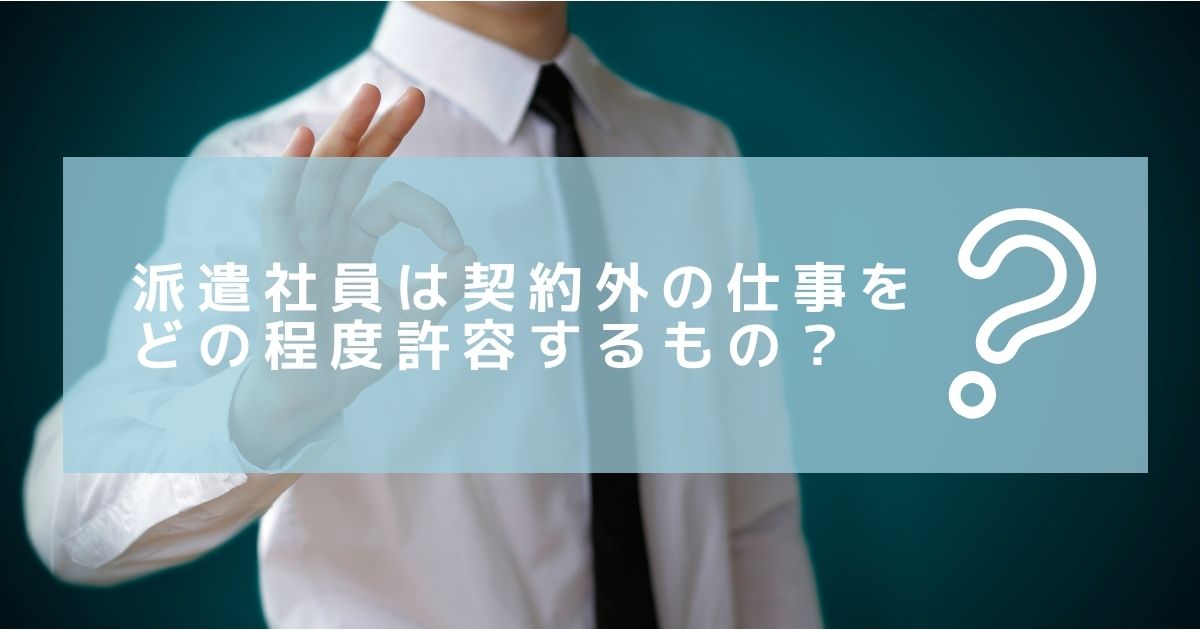
派遣先の視点から派遣社員にやらせてはいけない業務を解説してきましたが、逆に派遣社員側の立場からすると「自席の掃除くらいは許容範囲内」「派遣先に長く在席したいから、無理のない範囲で許容しなければ」という考えもあるでしょう。
では、実際に一般的に許容するラインはどこか考えてみましょう。
契約業務に影響がない程度で、決して我慢はしないこと
わかりやすいのが「本来の契約業務に支障が出ないか」という点です。
例えば、派遣先の社員がどうしても小一時間ほど不在になってしまい、一時的に電話番を任される、といった短期的な業務です。
「派遣社員だから」という理由で断るばかりでは、派遣先にあまりよいイメージを与えないのも事実ですので、本来契約している業務に大きな支障が出ない範囲内で受け入れるのは決して悪いことではありません。
ただし、小さなことが積み重なればストレスにもなりかねませんので、我慢は厳禁です。
契約外業務を指示された場合は拒否権がある
基本的に契約外業務を指示された場合、派遣社員には拒否権がありますので、任される内容を全て受け入れる必要はありません。
例えば、契約外業務でトラブルになる例には、以下のようなものがあります。
- 契約にない掃除やコピーなどの雑用を任される。
- 契約にない残業をお願いされる。
- 契約にある「~など」の部分に当てはまる業務だと言われる。
契約書で明記されていない業務に対して「これくらいやってよ」とどんなに言われても、契約違反でしかありませんし、断っていいのです。
契約にない仕事を指示された場合はどうすればいい?
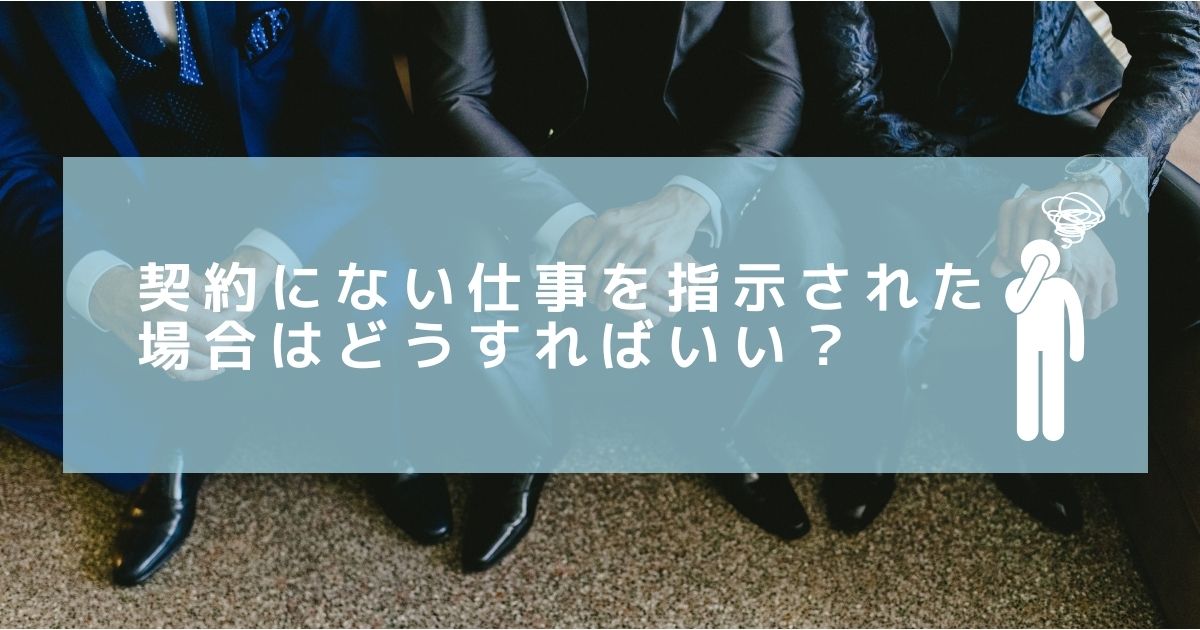
契約外の仕事を指示された場合には、まずは派遣会社に契約内容を確認し、契約に無い仕事と判断したら仕事を断ることが重要です。自身で断りにくい時には、派遣会社から伝えてもらうよう依頼しましょう。
以下の具体例のように、「契約内容にない業務とは何か」と困っている旨をしっかり担当者に伝えるようにしてみてください。

派遣先で契約内容にない営業の方のコピーやお茶くみなどの雑用を与えられていて、契約にある会計事務の業務に支障が出て困っています。派遣先に業務改善をお伝えいただきたいです。
契約にない仕事を派遣社員に指示することは契約違反にあたり、派遣先企業にもメリットはありません。
労働者と企業の信頼関係を築くためには、労働者が契約内容を把握しておくことが大切です。
派遣社員で契約にない仕事について解決しなかったときはどうする?
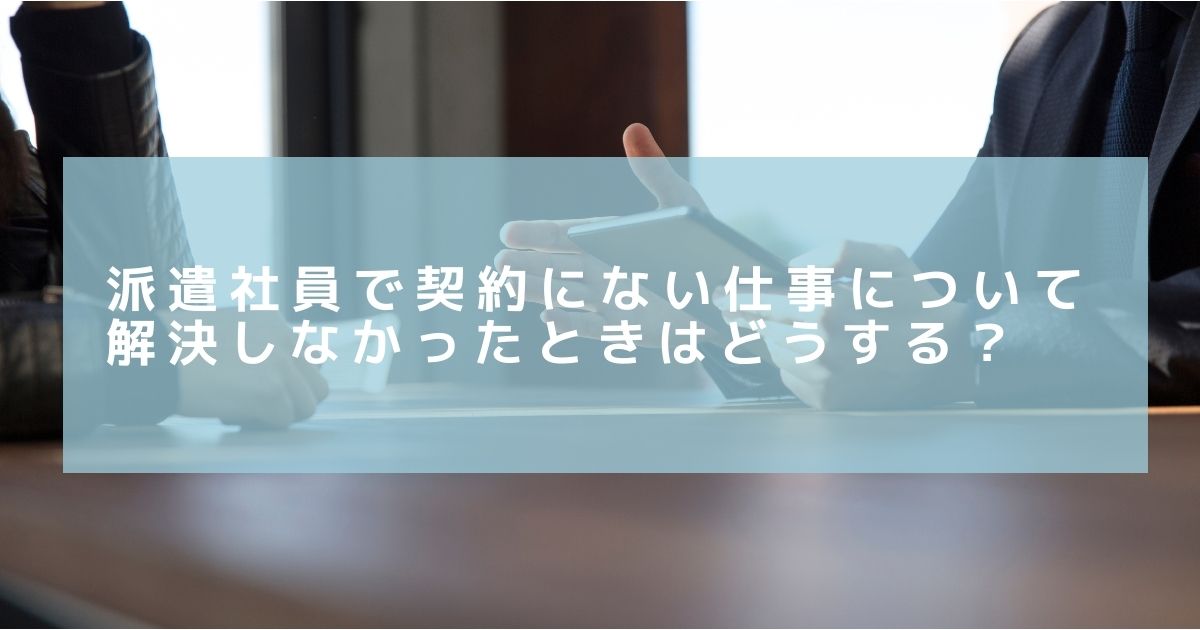
派遣労働者は、派遣法をはじめとした法令で、禁止されている業務や契約外の業務をすることが認められていません。
派遣先に断りを入れても業務改善されない、もしくは拒否されるようであれば、一刻も早く逃げる選択肢をおすすめします。
もし派遣先以前に派遣会社に相談して改善してもらえない場合は、担当者や派遣会社の変更が優先ですし、派遣のトラブルに疲れた場合は、いっその事しがらみのない正社員に転職してしまいましょう。
転職活動をする際、転職エージェントを利用すれば転職活動のサポートをしてくれるだけでなく、入社後の契約内容について交渉のアフターフォローをしてくれる所もありますので、不安な方はひとつのポイントとしてみてください。
派遣社員から正社員への転職でおすすめのサービス
「派遣社員から正社員への転職は大変…」と悩んでいた方は通常の転職サイトではなくアドバイザーが付く転職サービスを利用するのがおすすめです。
通常の転職サイトでは自分で全ての管理をする必要がありますが、アドバイザーが付くサービスの場合は面接までのスケジュール・添削・年収交渉などをしてくれるため、転職活動の負担を大きく減らしながら進めることができるからです。
負担を減らすだけではなく効率的に進めることができるので、結果的に短期間での内定獲得に繋がります。
転職サービスは複数利用がおすすめ
転職活動をする方の多くは2つ~3つの転職サイトを複数登録していることが多く、実際にそのような転職方法はおすすめです。
その理由としては各サイトによって求人内容が異なるので、なるべくその時々で良い条件の求人を確認できるからです。
また、転職をサポートしてくれるアドバイザーと相性が合う合わないという問題もあるため、なるべく一つの転職サービスだけではなく複数を利用することで客観的な判断がしやすくなります。
【業界最大手】リクルートエージェント

| 対象の年代 | 20代~50代 幅広い年代に対応 |
|---|---|
| どんな人に向いている? | ・とにかく多くの求人を見たい方 ・既卒、第二新卒の方 ・積んだキャリアを生かして転職したい方 ・エージェントから転職活動のサポートを受けたい方 |
リクルートエージェントは転職サービスの中で最も取り扱い求人数が多い、大手転職エージェントです。
取り扱い求人数が多いということは色々な可能性を見つけることができるため「次にやりたい仕事がまだイマイチ決まっていない」という方に合っています。
全国の求人を扱っているので、地域を選ばずに利用できるのもメリットの一つです。リクルートエージェントは転職を決意したらまず利用したい転職サービスです。
【派遣・未経験・フリーターから正社員へ】JAIC

| 対象の年代 |
20代~40代 |
|---|---|
| どんな人に向いている? | ・派遣社員、フリーター、既卒で早期退職を経験した方 ・未経験職種へのチャレンジをしたい方 ・社会人経験がない方 ・履歴書や面接に自信がない方 |
JAICはフリーターの方や就職をしたけど早期退職をするなど上手く行かなかった方、未経験職種や業界にチャレンジをしたい方におすすめの転職サイトです。
これから正社員を目指すという方を支援するためのプログラムや、アドバイザーからの丁寧な個別サポートを受けることができるので、「正社員への転職活動をしたいけど何をしたらいいのかわからない」という悩みを抱えていた方でも安心して転職活動を進めることができます。
また、転職成功率が高いだけではなく、入社後の定着率が高いこともJAICの特徴です。
内定を取ることだけを考えるのではなく、自分にとって働きやすい環境の会社をしっかり紹介してくれることが定着率の高さに繋がっていると言えるでしょう。
「これから正社員を目指したい」と考えていた方は要チェックの転職サイトです
【待ちの転職活動】ミイダス

| 対象の年代 |
20代~40代 特に20代に強い |
|---|---|
| どんな人に向いている? |
・第二新卒の方 |